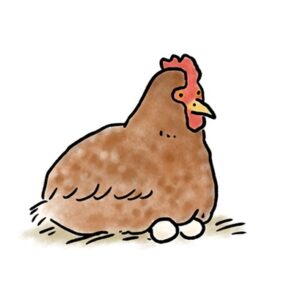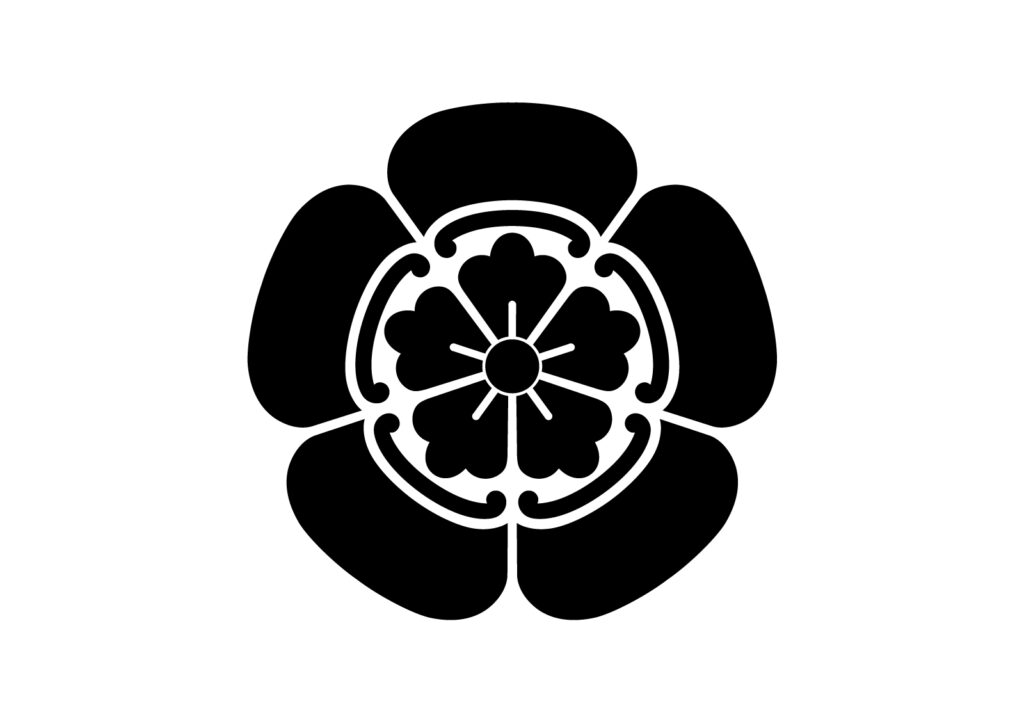第七十二候 雞始乳(にわとりはじめてとやにつく)【24大寒-末候】1月30日~2月3日
鷄が卵を産み始める時期。とやは「鳥屋」、鳥を飼っておく小屋。
・いたづらに寝る夜の夢をいさめてや ここに鳴ふる鶏の声ー後柏原天皇
・夜をこめて鳥の空音は謀るとも よに逢坂の関は許さじー清少納言『後拾遺集』
【旬】
木:柊(ひいらぎ)
ギザギザの葉が特徴的な木。昔はひりひり痛むことを「疼ぐ(ひいらぐ)」といい、そこから「柊(ひいらぎ)」になった。白く小さな花が付く。
木:海桐(とべら)
元々は海岸沿いに生える木で、最近では町にも植えられている。