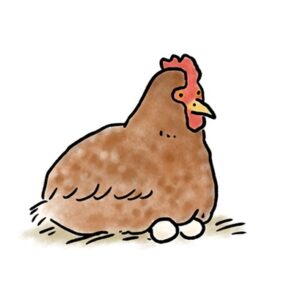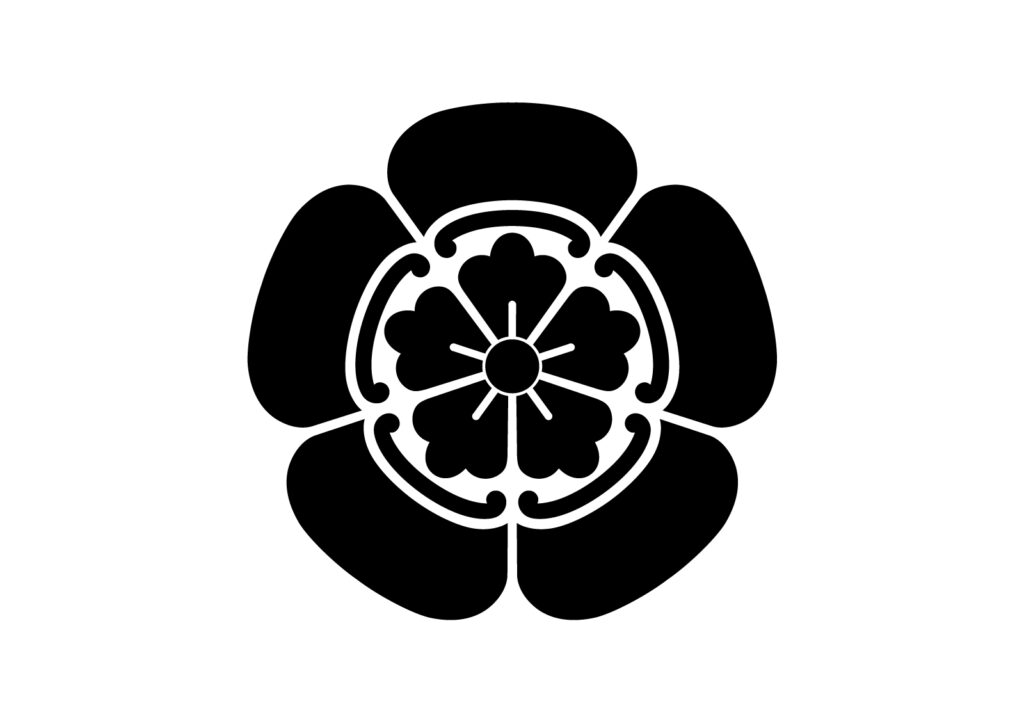| (春) 立春 2/4 雨水 2/19 啓蟄 3/5 春分 3/20 清明 4/5 穀雨 4/20 |
(夏) 立夏 5/5 小満 5/20 芒種 6/5 夏至 6/20 小暑 7/5 大暑 7/20 |
(秋) 立秋 8/5 処暑 8/20 白露 9/5 秋分 9/20 寒露 10/5 霜降 10/20 |
(冬) 立冬 11/5 小雪 11/20 大雪 12/5 冬至 12/20 小寒 1/5 大寒 1/20 |
対応する候
七十二候
(春)
1.立春(りっしゅん)(2/5)
・第一候 東風解凍(はるかぜこおりをとく)2/4~2/8
・第二候 黄鶯睍睆(うぐいすなく)2/9~2/13
・第三候 魚上氷(うおこおりをいずる)2/14~2/17
2.雨水(うすい)(2/20)
・第四候 土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)2/19~2/23
・第五候 霞初靆(かすみはじめてたなびく)2/23~2/27
・第六候 草木萌動(そうもくめばえいずる)2/28~3/4
3.啓蟄(けいちつ)(3/5)
・第七候 蟄虫啓戸(すごもりのむしとをひらく)3/5~3/9
・第八候 桃始笑(ももはじめてさく)3/10~3/14
・第九候 菜虫化蝶(なむしちょうとなる)3/15~3/19
4.春分(しゅんぶん)(3/20)
・第十候 雀始巣(すずめはじめてすくう)3/20~3/24
・第十一候 桜始開(さくらはじめてひらく)3/25~3/29
・第十二候 雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす)3/30~4/4
5.清明(せいめい)(4/5)
・第十三候 玄鳥至(つばめきたる)4/5~4/9
・第十四候 鴻雁北(こうがんかえる)4/10~4/14
・第十五候 虹始見(にじはじめてあらわる)4/15~4/19
6.穀雨(こくう)(4/20)
・第十六候 葭始生(あしはじめてしょうず)4/20~4/24
・第十七候 霜止出苗(しもやみてなえいずる)4/25~4/29
・第十八候 牡丹華(ぼたんはなさく)4/30~5/4
(夏)
7.立夏(りっか)(5/5)
・第十九候 鼃始鳴(かわずはじめてなく)5/5~5/9
・第二十候 蚯蚓出(みみずいずる)5/10~5/14
・第二十一候 竹笋生(たけのこしょうず)5/15~5/20
8.小満(しょうまん)(5/21)
・第二十二候 蚕起食桑(かいこくわをはむ)5/21~5/25
・第二十三候 紅花栄(べにばなさかゆ)5/26~5/30
・第二十四候 麦秋至(むぎのときいたる)5/31~6/4
9.芒種(ぼうしゅ)(6/5)
・第二十五候 蟷螂生(かまきりしょうず)6/5~6/9
・第二十六候 腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる)6/10~6/14
・第二十七候 梅子黄(うめのみきばむ)6/15~6/20
10.夏至(げし)(6/21)
・第二十八候 乃東枯(なつかれくさかるる)6/21~6/25
・第二十九候 菖蒲華(あやめはなさく)6/26~6/30
・第三十候 半夏生(はんげしょうず)7/1~7/7
11.小暑(しょうしょ)(7/7)
・第三十一候 温風至(あつかぜいたる)7/7~7/11
・第三十二候 蓮始開(はすはじめてひらく)7/12~7/16
・第三十三候 鷹乃学習(たかすなわちがくしゅうす)7/17~7/22
12.大暑(たいしょ)(7/23)
・第三十四候 桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)7/23~7/27
・第三十五候 土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)7/28~8/1
・第三十六候 大雨時行(たいうときどきにふる)8/2~8/6
(秋)
13.立秋(りっしゅう)(8/7)
・第三十七候 涼風至(すずかぜいたる)【13立秋-初候】8/7~8/11
・第三十八候 寒蝉鳴(ひぐらしなく)【13立秋-次候】8/12~8/16
・第三十九候 蒙霧升降(ふかききりまとう)【13立秋-末候】8/17~8/22
14.処暑(しょしょ)(8/23)
・第四十候 綿柎開(わたのはなしべひらく)8/23~8/27
・第四十一候 天地始粛(てんちはじめてさむし)8/28~9/1
・第四十二候 禾乃登(こくものすなわちみのる)9/2~9/6
15.白露(はくろ)(9/7)
・第四十三候 草露白(くさのつゆしろし)9/7~9/11
・第四十四候 鶺鴒鳴(せきれいなく)9/12~9/16
・第四十五候 玄鳥去(つばめさる)9/17~9/22
16.秋分(しゅうぶん)(9/23)
・第四十六候 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ)9/23~9/27
・第四十七候 蟄虫戸?(むしかくれてとをふさぐ)9/28~10/27
・第四十八候 水始涸(みずはじめてかれる)【16秋分-末候】10/3~10/7
17.寒露(かんろ)(10/8)
・第四十九候 鴻雁来(こうがんきたる)【17寒露-初候】10/8~10/12
・第五十候 菊花開(きくのはなひらく)【17寒露-次候】10/13~10/17
・第五十一候 蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり)【17寒露-末候】10/18~10/22
438″>18.霜降(そうこう)10/23(秋6)
・第五十二候 霜始降(しもはじめてふる)【18霜降-初候】10/23~10/27
・第五十三候 霎時施(こさめときどきふる)【18霜降-次候】10/28~11/1
・第五十四候 楓蔦黄(もみじつたきばむ)【18霜降-末候】11/2~11/6
・第五十五候 山茶始開(つばきはじめてひらく)【19立冬-初候】11/7~11/11
・第五十六候 地始凍(ちはじめてこおる)【19立冬-次候】11/12~11/16
・第五十七候 金盞香(きんせんかさく)【19立冬-末候】11/17~11/21
・第五十八候 虹蔵不見(にじかくれてみえず)【20小雪-初候】11/22~11/26
・第五十九候 朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)【20小雪-次候】11/27~12/1
・第六十候 橘始黄(たちばなはじめてきばむ)【20小雪-末候】12/2~12/6
・第六十一候 閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)【21大雪-初候】12/7~12/11
・第六十二候 熊蟄穴(くまあなにこもる)【21大雪-次候】12/12~12/16
・第六十三候 ?魚群(さけのうおむらがる)【21大雪-末候】12/17~12/21
・第六十四候 乃東生(なつかれくさしょうず)【22冬至-初候】12/22~12/26
・第六十五候 麋角解(さわしかつのおつる)【22冬至-次候】12/27~12/31
・第六十六候 雪下出麦(ゆきわたりてむぎのびる)【22冬至-末候】1/1~1/4
・第六十七候 芹乃栄(せりすなわちさかう)【23小寒-初候】1/5~1/9
・第六十八候 水泉動(しみずあたたかをふくむ)【23小寒-次候】1/10~1/14
・第六十九候 雉始?(きじはじめてなく)【23小寒-末候】1/15~1/19
・第七十候 ?冬華(ふきのはなさく)【24大寒-初候】1/20~1/24
・第七十一候 水沢腹堅(さわみずこおりつめる)【24大寒-次候】1/25~1/29
・第七十二候 ?始乳(にわとりはじめてとやにつく)【24大寒-末候】1/30~2/3
七十二候一覧
| (春) | (夏) | (秋) | (冬) |
| 東風解凍 黄鶯睍睆 魚上氷 土脉潤起 霞初靆 草木萌動 蟄虫啓戸 桃始笑 菜虫化蝶 雀始巣 桜始開 雷乃発声 玄鳥至 鴻雁北 虹始見 葭始生 霜止出苗 牡丹華 |
鼃始鳴 蚯蚓出 竹笋生 蚕起食桑 紅花栄 麦秋至 蟷螂生 腐草為蛍 梅子黄 乃東枯 菖蒲華 半夏生 温風至 蓮始開 鷹乃学習 桐始結花 土潤溽暑 大雨時行 |
涼風至 寒蝉鳴 蒙霧升降 綿柎開 天地始粛 禾乃登 草露白 鶺鴒鳴 玄鳥去 雷乃収声 蟄虫戸坯 水始涸 鴻雁来 菊花開 蟋蟀在戸 霜始降 霎時施 楓蔦黄 |
山茶始開 地始凍 金盞香 虹蔵不見 朔風払葉 橘始黄 閉塞成冬 熊蟄穴 鱖魚群 乃東生 麋角解 雪下出麦 芹乃栄 水泉動 雉始雊 欵冬華 水沢腹堅 雞始乳 |
第七十二候 雞始乳(にわとりはじめてとやにつく)【24大寒-末候】1月30日~2月3日
第七十一候 水沢腹堅(さわみずこおりつめる)【24大寒-次候】1月25日~1月29日
第七十一候 水沢腹堅(さわみずこおりつめる)【24大寒-次候】1月25日~1月29日
沢に水が厚く張り詰める頃。水沢(すいたく)は水のある沢。厳寒の時期、厚い氷には周りの景色が映る。それを氷面鏡(ひもかがみ)という。

【旬】
風物:氷柱(つらら)
滑るような感じを表す「つらつら」が変化したもの。
清少納言は「水晶の滝」にたとえて美しさをたたえている。
「 銀(しろがね)などを葺きたるやうなるに、水晶の滝など言はましやうにて長く短く、ことさらにかけわたしたると見えて、いふにもあまりてめでたきに・・」
(訳:屋根は白銀を葺いたような美しさで「水晶の滝」などと言いたくなる様子で、つららが長かったり短かったり、趣きのあるように掛け渡しているように見えて言葉にできない美しさで・・)
花:蝋梅(ろうばい)
梅の花のような馥郁(ふくいく)とした香り。「唐梅」「南京梅」などとも呼ばれた。
中国では梅、椿、水仙、蝋梅を「雪中の四友(しゆう)」とも呼ぶ。
風:虎落笛(もがりぶえ)
あたりの空気を引き裂くような音はさながら冬のクライマックス。
第七十候 欵冬華(ふきのはなさく)【24大寒-初候】1月20日~1月24日
24.大寒(だいかん)1月20日(冬6)
24.大寒(だいかん)1月20日(冬6)
二十四節気の最後、大寒です。一年で最も寒い時期。最低気温もこの時期になることが多いようです。
寒稽古、寒中水泳など寒のうちに体を鍛えると丈夫になる言われています。また寒海苔、寒卵など、寒のうちに生まれたものは上質だったり。厳しい寒さを乗り越えることで不思議な力が宿るのかもしれません。
大寒
第七十候 欵冬華(ふきのはなさく)【24大寒-初候】1月20日~1月24日
第七十一候 水沢腹堅(さわみずこおりつめる)【24大寒-次候】1月25日~1月29日
第七十二候 雞始乳(にわとりはじめてとやにつく)【24大寒-末候】1月30日~2月3日
第六十九候 雉始雊(きじはじめてなく)【23小寒-末候】1月15日~1月19日
第六十九候 雉始雊(きじはじめてなく)【23小寒-末候】1月15日~1月19日
キジが鳴きはじめる時期。雉は日本の国鳥。オスが「ケン、ケン」と甲高く鳴き、美しい羽を「ホロロ」と打ち鳴らす。

「けんもほろろ」は冷たく無愛想に(断る)という意味だが、雉の鳴き声が無愛想だからだとも言われる。
父母のしきりに恋し雉の声ー芭蕉
(ちちははのしきりにこいしきじのこえーばしょう)
【旬】
行事:小正月(こしょうがつ)
旧暦では1月15日が一年で最初の満月の日。この日を祝った名残が各地に残る。「餅花」「小豆がゆ」「どんど焼き」など。成人式が行われる時期でもある。
作物:小豆
鳥:尉鶲(じょうびたき)
第六十八候 水泉動(しみずあたたかをふくむ)【23小寒-次候】1月10日~1月14日
第六十八候 水泉動(しみずあたたかをふくむ)【23小寒-次候】1月10日~1月14日
地中では、凍った泉が動き始める時期と解釈されている。「水泉(すいせん)」は湧き出る泉のこと。地下水は普通凍ることはないが、昔の人は氷が溶け始めたと思ったのかも。

【旬】
風物:日向ぼっこ
海藻:昆布
こんぶの語源はアイヌ語の「kombu」からとも。
行事:鏡開き